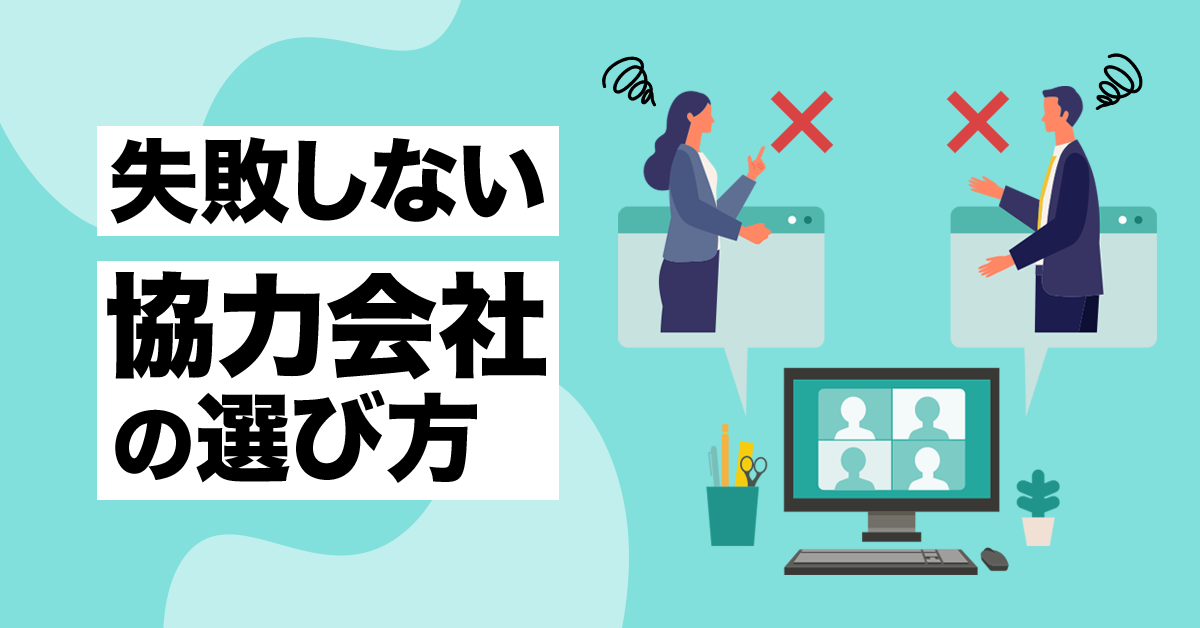マーケティングは経営そのもの。経営視点の持ち方。
更新日:2022.4.15 公開日:2021.6.29
マーケターにとって、切っても切り離せない関係にあるのが経営者です。
「マーケティングは経営そのもの」と言っている人がいるぐらい、マーケティング活動の成否が会社の未来を決めるといっても過言ではありません。
それだけ重要なマーケティング業務だからこそ、経営者からの関心も高く、様々な意見(ダメ出し含む)を日々もらっている方が多いのではないでしょうか。
こうした状況下にいるマーケターの中には
「一生懸命進めているにもかかわらず、なんでダメ出しされないといけないんだ…」
「こっちからの提案は却下するのに、自分の意見ばかり言ってきて…」
と心の中で思っている方がいるかもしれません。
そんな方はぜひ見方を変えてみてください。
経営者がそれだけマーケティングに興味・関心を持っているということは、経営者のバディ(味方)になることで新しいマーケティング施策の承認が下りたり、予算を増額してくれたりと、様々なメリットが得られる可能性を秘めていることになります。
今回は経営者のバディになるために必要な「経営視点」について、持たないと起きてしまう課題や身につけるために必要なポイントをお伝えしていきます。
そもそも「経営視点」とは何か?
まずは経営という言葉の意味から考えていきます。
抽象的な言葉でもあるので、改めて聞かれるとどんな意味か分からないという方も多いのではないでしょうか。
辞書で「経営」という言葉を調べると、以下のような説明になっています。
「事業目的を達成するために、継続的・計画的に意思決定を行って実行に移し、事業を管理・遂行すること。また、そのための組織体。(goo辞書)」
「継続的・計画的に事業を遂行すること。特に、会社・商業など経済的活動を運営すること。また、そのための組織。(広辞苑)」
そして、この経営をしているのが「経営者」であり、経営者が見ている視点が「経営視点」ということになります。
つまり、経営視点というのは、事業目的を達成するための意思決定や経済的活動を運営するために必要なものです。
事業を運営し成功に導くためには、マーケティングはもちろん、売上やコストなどの財務・会計、すべての部署や従業員のマネジメント、企業を成長させるための経営戦略など、あらゆる情報を俯瞰的に見ていくことが必要であり、それこそが「経営視点」と言えます。
ではこの経営視点をマーケターが持っていないと、どんな課題が起きてしまうのでしょうか。
経営視点を持たないと発生する課題
マーケティング業務は戦略策定から施策の立案、日々の広告運用や数値管理まで幅広いです。特にマーケティング組織が小さい場合には、そのすべてを担当しなければなりません。
結果として日々の業務に忙殺されてしまい、目の前のことで精一杯になってしまっている方も多いのではないでしょうか。
そのような状況では経営視点を持つのは難しく、以下のような事象が起きてしまいます。
部分最適の施策ばかり立案してしまう
マーケティングは商流において上流に位置していることが多く、本来は「部分最適」ではなく「全体最適」となる施策を立案する必要があります。
しかし、目先の業務だけに囚われてしまうと、
・今目の前にある課題だけを解決する施策になってしまう
(理想は複数の課題の中から優先順位をつけて設定する)
・マーケティングの成果だけを追い求めた施策になってしまう
(理想は最終的な受注や売上といった成果を達成するための施策を設定する)
など自分も気付かぬうちに部分最適となる施策を立てていることは少なくありません。
このような状況に陥ると、何が起きてしまうのでしょうか?
施策の承認が下りない/予算がもらえない
経営者が見ている領域はマーケティングだけではありません。
営業や商品開発、人事・総務など社内のすべての業務に目を配りながら会社を運営しています。
つまり、施策や予算を承認するかどうかは、
「ある一つの業務(部門)の成果が最大化するか?」ではなく
「全社で目指している成果が最大化するか?」という基準のもとに判断が下されます。
この基準を考えれば、場当たり的な施策やマーケティングのみの成果を追い求めた施策が承認されないのは理解できるはずです。
では施策や予算を承認してもらえるようになるためには何が必要になるのでしょうか。
マーケターが持つべき経営視点とは
本当の意味で会社に貢献し、成果を出すことができるマーケターになるためには経営者と同じ視点を持たなくてはなりません。
ここからはマーケターが持つべき経営視点を2つ(+α)ご紹介します。
1. マーケティング課題だけではなく経営課題は何かを考える
まず最初に押さえるべきは「会社としてどのような経営課題を抱えているのか」です。
マーケターであれば自社のマーケティング課題は把握しているはずです。
しかし、他部署の状況までは把握しきれておらず、会社全体を見たときに優先度の高い経営課題は分からないという方が多いのではないでしょうか。
以下のような状況のとき、ご自身ならどういうマーケティング施策を立てますか?
・営業部のベテラン社員が相次いで退職してしまい、現在は若手中心でギリギリ回している
・ベテラン社員がいた頃は確度が低いリードであっても商談にさえ繋げればなんとかなった
・実力不足のメンバーがほとんどで、社内には営業力を育成できるリソースがない
・急ピッチでマネージャークラスの営業パーソンの採用活動を行っているが、現段階で採用の目途は立っていない
・期末も近づいており、ここから新規受注を複数案件とらないと全社売上の目標達成が危うい
この状況下であれば、質より量を重視して多くのリードを獲得しようとは思わないですよね。
しかし、会社として抱えている経営課題を把握できていないと、「マーケティングの目標はリード獲得だからとにかく数を取れる施策を実施しよう」になってしまいます。
これでは経営者のバディになれないだけでなく、施策の承認も下りないので注意しましょう。
2. 「短期」と「長期」どちらの視点も持ち続ける
マーケターに必要なスキルの一つとして、先読みや先見性といったトレンドを見抜く力があります。
そのため多くのマーケターは長期的な視点を持って、施策を立案しているのではないでしょうか。しかし、経営視点を持つためには「長期」の視点だけでは足りません。
なぜなら経営者は常に「短期」と「長期」どちらの視点も求められるからです。
例えば上場している会社であれば、四半期に1回株主に対して報告書を開示しなければなりません。非上場企業についても銀行から融資を受けていれば、銀行に対して業績の説明をする必要があります。
もちろん、株主や銀行も長期的な成果を期待したうえで投資していますが、「目先の売上や利益はどうなっているのか」など短期の成果への関心度は非常に高く、あまりにも短期の結果が出ていなければ投資や融資を止められてしまうこともあります。
だからこそ、経営者は短期の成果をしっかりと追い求めつつ、長期を見据えて様々な施策を行っていく必要があるわけです。
マーケターが経営者と同じ目線で仕事をするためには、短期と長期どちらの視点もバランスよく持てるようになることが求められます。
+α 経営者の真のバディになるために
まず押さえるべきは上記の2つなのですが、経営者のバディとしてさらなる価値を発揮したい方は「財務・会計」に関する視点も持てるようになるとよいでしょう。
財務・会計が必要な理由として、事業を成功に導いていくためには利益を最大化することが求められます。マーケティング業務に携わっていると、売上を最大化することに目が行きがちですが、「利益=売上-コスト」のためコストに関する視点を併せて持つことで、より全社目線で物事をとらえることができます。
経営者はこのコストも含めた財務面を非常に気にかけているため、マーケターが同じ目線をもってくれれば安心して仕事を任せてくれるでしょう。
経営視点を持つためにマーケターがすべきこと
ではここからは経営視点を持てるようになるために、どのようなアクションをとればよいのか見ていきます。
経営者との定期的なディスカッションの機会を設ける
このディスカッションというのは、単なるマーケティング成果の数値共有を行うことではありません。全社で抱えている課題について経営者からヒアリングを行い、マーケティング全般についてのディスカッションを行いましょう。
ヒアリングを行う際は、経営者の頭の中を可視化するイメージで、以下の質問例を参考に実施してみてください。
・現在、会社として抱えている経営課題は何なのか
・これからどういった優先順位をつけて解決していこうと思っているのか
・マーケティングで力になれる部分はどこにあるのか
そしてヒアリング後の重要なポイントは、認識のすり合わせを必ず行うことです。
一度話を聞いただけで、完璧に理解することは難しいでしょう。
聞いたことを自分の言葉で再度確認し、不明点は積極的に質問することで、より深く経営者の視点を理解できます。
そして、「今の話を踏まえて、私はこのような施策をやってみようと思っていますがどうでしょうか?」など自分の意見を伝えるようにしましょう。
経営者からも色々な角度から意見をもらえるので施策をブラッシュアップできるのはもちろん、新しい施策のタネが出てくるかもしれません。
他部門のマネージャーとも積極的にディスカッションする
コミュニケーションをとる必要があるのは経営者だけではありません。
会社全体で抱えている課題やそれに対する優先順位は、経営者とのディスカッションで把握できます。
その一方、各部門が抱えている課題の詳細までは分からないため、各部門のマネージャーとも積極的ディスカッションをする必要があります。
特にマーケティング活動と関連性が高い、インサイドセールス部門やフィールドセールス部門、カスタマーサクセス部門、商品開発部門などのマネージャーとは定期的に意見交換を行うとよいでしょう。
例えばインサイドセールス部門であれば、
「直近のリードの質について変化はあるか?」
「今後このようなマーケティング施策を行う予定だが、お客様がどう思うか意見が欲しい」
などを聞いてみるといいかもしれません。
お客様との接点数が多い部署だからこそ、意見交換をする中でニーズのトレンドを掴むことができ、新しいマーケティング施策の立案や優先順位付けに活かすことができます。
またリードの質が下がっているなどの情報を早期にキャッチアップすることができれば、部分最適ではなく全社最適の施策になるよう、先手先手で様々な工夫を行えるようになります。
こうした他部門からの意見を収集する際には、メンバーではなくマネージャーとコミュニケーションをとると、全体感が分かりやすいのでおすすめです。
経営者・他部門マネージャーとディスカッションするときのポイント
経営者はもちろん、他部門のマネージャーも日々忙しく仕事をしているはずです。
せっかく時間をもらってディスカッションをしても、こちらの段取り不足でグダグダになってしまうと2回目以降の機会をもらえなくなってしまうかもしれません。
以下のポイントを押さえて有意義なディスカッションとなるように心がけてみてください。
【準備編】
1. ディスカッションは突然声をかけて行うのではなく、事前に会議申請をして時間を確保する
2. 質問したいことは書き起こし、事前に共有する
3. 経営方針や部門方針など、既に公表されているものは事前に確認しておく
【当日編】
4. 冒頭にディスカッションの目的とアジェンダを説明する(ディスカッションをしている中で方向性がずれていく可能性があるため、ここはとても重要です)
5. 相手の発言は否定せずに傾聴することを心がける
6. 知ったかぶりはせず、初歩的な内容でも必ず質問をする
7. 発言内容は録音・録画する、議事録をとるなどして記録に残す
8. マーケティングの現状について説明するときは専門用語は使わずに相手が理解しやすいように話す
まとめ
マーケティングは会社にとって非常に重要な役割を担っています。
だからこそ、マーケターが経営視点を持ち、経営者のバディになることができれば、全社の成果に対してさらに貢献ができるはずです。
そして自部門だけなく他部門の状況や課題を把握できれば、常に先手で全体最適な施策の立案を行えます。
今回ご紹介したポイントをもとに、少しずつ経営視点を身につけ、マーケティングの成果向上にお役立てください。
タグ: 組織開発
ピクルス / マーケターのバディ
ピクルスのTwitterアカウントで、毎日、
マーケティングに関しての「今日の発見」を発信中!
@pickles_incさんをフォロー
関連記事
-
プリンセス・マーケティングとは|女性の消費行動を理解する7つのポイント
更新日:2023.8.17 公開日:2022.5.13
-
優秀なマーケターが愛用する「プロダクトローンチ」とは|爆発的に売上を伸ばした事例を紹介
更新日:2022.11.21 公開日:2021.9.21
-
2022年4月改正「個人情報保護法」をマーケティング目線でポイント解説
公開日:2022.8.2
-
マーケティングにペルソナを活用する効果とは?よく聞く3大疑問にズバッと回答
更新日:2022.11.24 公開日:2022.3.8
-
失敗しない協力会社の選び方:業務委託先を見極めよう
更新日:2022.8.2 公開日:2021.5.31
-
顧客インサイトとは?理解するための方法と成功事例から考える必要性
更新日:2022.12.26 公開日:2021.12.7